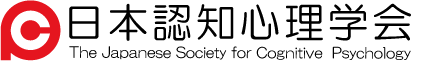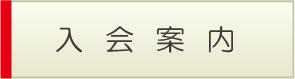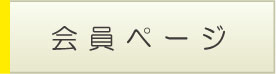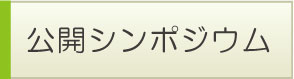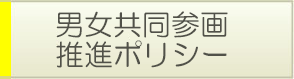『認知心理学研究』 第23巻 第1号(2025年8月)
目次
- 原著/ブランド・パーソナリティに基づく感覚間転移の生起可能性(久保夏海・松下光司・有賀敦紀)
- 原著/創造的問題解決における評価予期と人型会話ロボット活用の効果(安陪梨沙・服部雅史・林 勇吾)
- 原著/園生活における幼児の教示:自然観察に基づく検討(王 淳・外山紀子)
- 原著/Robot tears promote psychological anthropomorphism: A study with image stimuli(Akiko YASUHARA・Takuma TAKEHARA)
- 資料/A ruler-based technique to rigorously control the size of visual stimuli for online psychological experiments(Hiroyuki MUTO)
- 資料/青年期における視線認知について(山内裕斗・安藤美華代)
- 特別寄稿/2023年度日本認知心理学会独創賞記念論文日本語における色字共感覚研究(浅野倫子・横澤一彦)
- 学会参加報告/2024年度日本認知心理学会と韓国認知生物心理学会の交流:韓国大会への若年研究者派遣事業・報告(Yang CHEN)
- 会報
日本認知心理学会第23回総会報告
第24回大会のお知らせ
お知らせ
日本認知心理学会 会則
日本認知心理学会選挙細則
「認知心理学研究」諸規程
Abstract
原著/ブランド・パーソナリティに基づく感覚間転移の生起可能性
久保夏海(中央大学)
松下光司(学習院大学)
有賀敦紀(中央大学)
飲料を飲むとき,私たちは周囲の感覚情報を含めて味を評価している(感覚間転移).本研究では,ブランドの特徴やコンセプトに対して想起するイメージに人間の性格特性をあてはめたブランド・パーソナリティ(BP)に着目し,容器の飲み口の薄さから飲料の味への感覚間転移がBPによって促進され得るかを検討した.容器の飲み口の薄さと飲料の苦味は覚醒度の高い表象を介して連合していると考えられるため,同様に覚醒度の高いBP( Excitement次元)が喚起されることで,容器の薄さに関する視覚処理から苦味予測への感覚間転移は促進されると予測した.実験1, 2では,飲み口の薄いマグカップとExcitement次元との間に有意な連合があることが示された.実験3では,参加者がExcitement次元のカフェにいることを想像したとき,どのBPも喚起されなかったときと比較して,薄いマグカップに入ったコーヒーの苦味を強く予測した.これらの結果は,BPがマグカップの飲み口の薄さと連合があり,マグカップから予測するコーヒーの苦味への感覚間転移が,Excitement次元のBPによって生起する可能性を示している.
キーワード: ブランド・パーソナリティ,感覚間転移,消費者行動,飲料
原著/創造的問題解決における評価予期と人型会話ロボット活用の効果
安陪梨沙(立命館大学)
服部雅史(立命館大学)
林 勇吾(立命館大学)
本研究は,創造性課題の実施において人型会話ロボットが実験を進行することが,参加者の評価予期を軽減して創造性を高めるかを検討した.実験1では,36名の大学生が地球外生命体生成課題を実施した.実験者がロボットの場合(ロボット群),人間の場合(人間群)よりも,否定的評価に対する不安(特性評価不安)が高い参加者の独創性が低かった.これは予想に反する結果であったことから,原因を探るためインタビュー調査を実施した.その結果,特性評価不安の高い参加者は,ロボット実験者に気楽さを感じて独創性を高める努力をしなかったこと,人間の実験者が作品を評価する可能性と評価基準の不明確さによって努力を促されたことが示唆された.そこで実験2では,課題を評価基準の明確な拡散的思考課題に変更して,105名の大学生に同様の実験を実施した.その結果,ロボット群の方が人間群よりも緊張スコアは低く,課題成績はよかった.本研究は,実験者の種類と課題性質の違いが参加者の評価予期と創造性に異なる影響を与えることを明らかにした.
キーワード: 特性評価不安,状態評価不安,地球外生命体生成課題,拡散連想課題
原著/園生活における幼児の教示:自然観察に基づく検討
王 淳(早稲田大学大学院人間科学研究科)
外山紀子(早稲田大学人間科学学術院)
本研究では東京の保育園で自然観察を行い,幼児の教示を検討した.これまでの研究では幼児は大人の支援・指導のもとで学ぶ学習者として検討されることが多かったが,本研究では積極的に他者を教える教示者として幼児を捉えた.第一著者が保育ボランティアとして7ヶ月間,保育に参加しながら記録をとった.そ
の結果,幼児の教示の多くは幼児が自発的に行っていたこと,教示内容は宣言的知識や手続き的知識,ルールなど,そして教示方略は言葉による説明や実演など多岐にわたることが示された.ナチュラルペダゴジー理論では大人は乳児とコミュニケーションをとる際に「明示的手がかり」(注意喚起発話,指さし,ジェス
チャーなど)を用いることが示されているが,本研究では教示者である幼児もまたこれらの手がかりを頻繁に使用していることが示された.以上の結果は,幼児が就学前段階から有能な教示者としての能力を備えていることを示唆している.
キーワード: 教示,保育園,ナチュラル・ペダゴジー,自然観察
原著/Robot tears promote psychological anthropomorphism: A study with image stimuli
Akiko YASUHARA (Graduate School of Psychology, Doshisha University; Japan Society for the Promotionof Science)
Takuma TAKEHARA (Faculty of Psychology, Doshisha University)
ロボットの心理的擬人化は人がロボットという存在をどう扱うか決定するカギとなる.そこで,本研究はロボットの涙が心理的擬人化を促進するか検証することを目的とした.ロボットの画像に涙をデジタルで加工し,涙のある画像と涙のない画像を作成し視覚刺激とした.研究1ではロボットの画像を提示し,参加者
にロボットの社会性,主体性,アニマシー,不快感について回答を求めた.涙はアニマシーの評価を向上させたが他の変数に変化はみられなかった.研究2ではロボットの画像とロボットのおかれている状況(死と別れ)を記述した短いシナリオを提示し,研究1と同様の質問に回答を求めた.涙はアニマシーに加えて社
会性と主体性の評価も向上させた.したがって,本研究の結果はロボットの涙が心理的擬人化を促進する可能性があることを示しており,この効果には文脈が重要であることを示唆している.加えて,アニマシーが心理的擬人化の基礎的な側面の可能性がある.
キーワード: 感情的な涙,泣き,感情表現,擬人化,コミュニケーションロボット
資料/A ruler-based technique to rigorously control the size of visual stimuli for online psychological experiments
Hiroyuki MUTO (Graduate School of Sustainable System Sciences, Osaka Metropolitan University)
本研究は,オンライン心理学実験において視覚刺激のサイズを厳密に統制する方法を提案する.この方法では,ランダムな長さで提示される線分の長さを参加者に繰り返し物差しで測定させ,その測定値をもとに画面上のミリメートル:ピクセル比を最小二乗法で推定する.キャリブレーションの成功は,テスト用線分
の測定誤差や線形回帰モデルの残差分散によって客観的に評価できる.シミュレーションの結果,提案する通過基準のもとでは比の推定誤差の標準偏差が高々0.007 mm/pxであることが示された.この方法を実際に実装したところ,100人の参加者のほとんどが数分以内に手続きを完了でき,この方法の十分な実現可能
性が示唆された.本方法は,視覚刺激のサイズが鍵となる視知覚や視覚認知に関する現象をオンライン環境で研究する際に特に有用であると考えられる.この方法のデモとlab.jsで実装するためのJSONファイルをOSFで公開している(https://doi.org/10.17605/osf.io/zeyxp).
キーワード: オンライン実験,刺激サイズキャリブレーション,実験的統制,視知覚,方法論
資料/青年期における視線認知について
山内裕斗(岡山大学大学院社会文化科学研究科)
安藤美華代(岡山大学学術研究院社会文化科学学域)
本研究では日常的な場面に注目し,中学生,高校生,大学生という異なる発達段階において,「自分が他者に視線を向けていると思うこと(見る認知)」と「自分が他者から視線を向けられていると思うこと(見られる認知)」という視線に関する認知的な側面の関係について検討することを目的とした.質問票での調査を実施し,中学生285名,高校生285名,大学生308名を分析対象とした.見る認知と見られる認知,その時の不快感情との関連,またそれらの発達段階による差異の検討を行った.その結果,いずれの発達段階においても,見る認知と見られる認知,視線交錯の認知の正の相関が示され,視線認知間の関連が示された.また,見られる認知よりも見る認知の経験のほうが高く,見る認知時の不快感情よりも見られる認知時の不快感情のほうが高くなることが示された.また中学生や高校生よりも大学生のほうが見る認知の経験や見られる認知時の不快感情が高くなった.
キーワード: 視線認知,見る,見られる,発達段階
特別寄稿/2023年度日本認知心理学会独創賞記念論文
日本語における色字共感覚研究
浅野倫子(東京大学)
横澤一彦(日本国際学園大学)
色字共感覚とは,文字を見た際に,一般的な文字の認知処理に加えて,特定の色(共感覚色)の感覚経験も引き起こされる現象(認知特性)であり,一般人口のうちの少数の人のみに生じる.本稿では,2023年度日本認知心理学会独創賞の受賞に際し,著者らがこれまでに行ってきた日本語の色字共感覚研究を振り返って紹介する.学術的意義に関しては,特に,多種かつ多数の文字を日常的に使用する日本語の特性を生かした研究により,文字と共感覚色の対応関係の規定因を明らかにした点に独創性があると考える.また,共感覚は少数派の認知特性であることから,その研究成果の発信には社会的意義を伴うことについても考える.
キーワード: 色字共感覚,日本語文字,言語の認知処理