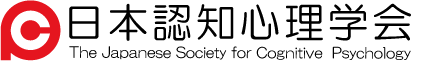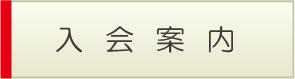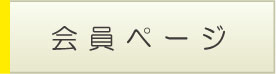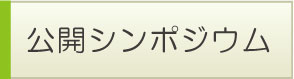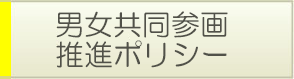第23回日本認知心理学会優秀発表賞の選考結果のお知らせ
日本認知心理学会優秀発表賞規程に基づき,選考委員会において慎重な審議を重ねた結果,発表総数件の中から,以下の5件の発表に優秀発表賞を授与することに決定しました.受賞者には第24回大会にて授与を行います.
2025年11月7日
※下記受賞者の所属表記はすべて,発表当時のものとなります.現在の所属と異なる場合もあります.ご了承いただけますと幸いです.
※お名前表記に*がある方は2025年11月7日時点での非会員です.次回大会時に予定されている授与式までに入会された場合には発表賞授与の対象となります.
【新規性評価部門】
受賞者(所属):内藤 優太1,河地 庸介1(1.東北大学大学院文学研究科)
発表題目: 重心の高さが重量感覚に与える影響
【技術性評価部門】
受賞者(所属):本田 秀仁1,香川 璃奈2(1.追手門学院大学 2.産業技術総合研究所)
発表題目: 関数学習の適応性と多様性―自己生成サンプルに基づく理論的・実証的分析―
【社会的貢献度評価部門】
受賞者(所属):晴木 祐助1, 2, 3, 4,*宮原 克典3,小川 健二2, 3,*鈴木 啓介3(1.東京大学大学院総合文化研究科 2.北海道大学文学院 3.北海道大学人間知・脳・AI 研究教育センター 4.日本学術振興会)
発表題目: スマートフォンへの注意バイアスと内受容感覚の低下および生理反応亢進の関連
【発表力評価部門】
受賞者(所属):鈴木 悠介1,永井 聖剛2(1.立命館大学 OIC 総合研究機構 2.立命館大学総合心理学部)
発表題目: 課題無関連な音声刺激に対する発声ピッチ収束
【国際性評価部門】
受賞者なし
【総合性評価部門】
受賞者(所属):武藤 拓之1,*鍵 直矢2(1.大阪公立大学大学院現代システム科学研究科 2.大阪府立大学現代システム科学域)
発表題目: 協力パートナー選択における個人手がかりと行動手がかりの統合過程―囚人のジレンマゲームを用いた検討―
以下,受賞研究の抄録と推薦理由です.
学会HPもご覧下さい. 日本認知心理学会優秀発表賞
【新規性評価部門】
受賞者(所属):内藤 優太1,河地 庸介1(1.東北大学大学院文学研究科)
発表題目: 重心の高さが重量感覚に与える影響
発表要旨: 物体の大きさが同じでも,重心位置の違いで主観的重量が変化し得る現象は,重い荷物をリュックサックの上部に配置すると軽く感じられる等の経験的知識として共有されているが,体系的な検討は皆無に等しい.そこで実験1では,158g–242gの錘を用いて,上重心または下重心の比較刺激を作成し,200gの下重心の標準刺激を基準として主観的等価点を算出した.その結果,上重心の刺激は下重心の刺激より軽く知覚されることが示された.実験2では,比較刺激の重心位置を上・中・下の3段階に操作し,下重心の標準刺激と比較してより重く感じられる刺激を選択するように求めた.その結果,重心が高いほど軽く感じられる一方,一定の高さを境に錯覚が減衰する可能性が示された.先行研究が物体の大きさが重量知覚に及ぼす影響に着目してきたのに対し,本研究は,大きさが一定でも重量感覚を変容させる要因として物体の重心位置が重要であることを示した.
選考理由: 「重い荷物をリュックサックの上に配置すると軽く感じる」という日常的観察を契機として,物体の重心位置が重さ弁別に及ぼす影響を実験心理学的手法により検討した研究である.従来のsize-weight illusionでは物体の大きさを視覚的に認識する必要性が指摘されていたが,本研究では閉眼状態であっても重さ弁別時(実験者が参加者の掌に錘を置く)に,低い重心の錘の方が高い重心の錘よりも重く知覚されることを示した.今後検討すべき点も少なくないが,感覚センシングの一端を明らかにした研究と言え,本研究は新規性部門の優秀発表賞にふさわしいと判断した.
【技術性評価部門】
受賞者(所属):本田 秀仁1,香川 璃奈2(1.追手門学院大学 2.産業技術総合研究所)
発表題目: 関数学習の適応性と多様性―自己生成サンプルに基づく理論的・実証的分析―
発表要旨: 本研究では,人間が自ら生成したデータ(自己生成サンプル)を再び学習に用いるという,新しい2変数間の関係性学習の実験パラダイムを提案した.この方法では,実験参加者自身が学習した内容を素材として用い,その手続きを繰り返すことによって,最終的にどのような関係性の学習が達成されるかを分析する点に特徴がある.まず,ベイズ線形回帰モデルを用いた計算機シミュレーションによる理論的分析では,このパラダイムにより,正確な関係性の学習だけでなく誤った関係性の学習も生じることが示された.そして認知実験においても同様に,全体として実験参加者は正確な関係性の学習を達成する一方で,誤った関係性を学習する例もしばしば観察され,理論的分析で示された傾向が実証的にも確認された.これらの結果は,自己生成サンプルに基づく実験パラダイムを用いることで,適応的および非適応的学習という認知の多様な側面を明らかできる可能性を示している.
選考理由:本研究は,2変数間の関数関係の学習に関して,学習者自身による関数関係の推定結果 (自己生成サンプル)を再び学習に用いるという新たな学習パラダイムを提案し,その学習過程を検討している.発表者はベイズ線形回帰モデル(Kalish et al., 2007)を理論モデルとした計算機シミュレーションを先立って実施し,真の関数関係の相関が弱い場合に強い正の相関が学習されるバイアスが生じうること,初期に呈示される学習サンプルが学習結果に影響しうることを確認した.認知実験では,計算機シミュレーションによる予測と概ね整合する形で同様の学習傾向が観察された.計算機シミュレーションと認知実験を効果的に組み合わせた本研究の手法は,新たな学習パラダイムにおける関数学習の認知メカニズムに迫る推論を可能にしている.また,一連の結果は,先行研究で提案された理論モデルの一般化可能性にも示唆を与えている.以上の理由より,当該研究の発表は技術性評価部門の優秀発表賞に値すると判断した.
Kalish, M. L., Griffiths, T. L. & Lewandowsky, S. (2007). Iterated learning: Intergenerational knowledge transmission reveals inductive biases. Psychonomic Bulletin & Review, 14 (2), 288–294. https://doi.org/10.3758/BF03194066
【社会的貢献度評価部門】
受賞者(所属):晴木 祐助1, 2, 3, 4,*宮原 克典3,小川 健二2, 3,*鈴木 啓介3(1.東京大学大学院総合文化研究科 2.北海道大学文学院 3.北海道大学人間知・脳・AI 研究教育センター 4.日本学術振興会)
発表題目: スマートフォンへの注意バイアスと内受容感覚の低下および生理反応亢進の関連
発表要旨: スマートフォンの過剰使用は不安・抑うつと関連し,その背後に依存症類似の神経生理基盤が指摘されている.本研究では,大学生58名を対象に,スマートフォン関連刺激への注意バイアスと内受容感覚・生理反応の関係を検討した.知覚負荷を操作した文字検出課題中,背景に課題非関連のスマートフォン/スクランブル画像を呈示し,心電計で心拍反応を記録,質問紙で内受容感覚と依存傾向を評価した.行動指標による自動クラスタリングにより,低負荷時のみスマートフォンが注意捕捉する群(32名)と,負荷に関わらず一貫して注意バイアスを示す群(26名)が同定された.後者は内受容への気づき・身体感覚への信頼が低く,スマートフォン依存傾向が高かった.さらに後者の群はスマートフォン刺激呈示に対し,前者と比較して心拍加速を示した.以上より,スマートフォンへの注意バイアスが内受容感覚の低下と生理的反応性の増大と関連することが示された.
選考理由: 本研究は,文字検出課題の反応時間に基づき,参加者を2群に分類している.課題中の心電図を記録し,参加者はスマートフォン依存と内受容感覚に関する質問紙に回答している.2群間の比較から,一貫してスマートフォンに注意補足される群(課題難易度に関わらずスマートフォン背景で文字検出が遅い群)は,スマートフォン依存傾向が高く,内受容感覚(身体感覚への気づき,身体感覚への信頼感の得点)が低く,スマートフォン画面提示後に心拍加速がみられることを示している.さらに薬物・ギャンブル依存症と共通するメカニズムや,スマートフォンの問題的使用の早期介入についても考察している.本研究は,今後さらに重要性を増すと考えられるスマートフォン依存のメカニズムを,注意,生理,内受容感覚など多面的な観点から明らかにしようとするものであり,応用的な展開も期待される.以上から,社会的貢献度評価部門の優秀発表賞にふさわしいと判断した.
【発表力評価部門】
受賞者(所属):鈴木 悠介1,永井 聖剛2(1.立命館大学 OIC 総合研究機構 2.立命館大学総合心理学部)
発表題目: 課題無関連な音声刺激に対する発声ピッチ収束
発表要旨: 他者音声に自己の発声音声が類似する現象は音声収束と呼ばれる.先行研究はシャドーイング課題を用いて,そのメカニズムを検討してきた.しかし,この課題では音声刺激が収束対象であると同時に発声開始キューとして機能するため,参加者は常に音声刺激に意図的に注意を向ける必要があった.そのため,既に発声計画が開始された後に提示される,課題無関連な音声刺激に対しても音声収束が生じるかは不明であった.本研究では,発声計画開始後に提示される音声刺激に対してピッチ収束が生じるかを検討した.参加者は発声開始キューに従いできるだけ速く発声するよう求められ,キュー提示直後には異なるピッチをもつ課題無関連音声刺激が提示された.その結果,刺激のピッチが高い場合に発声ピッチも高く,低い場合に低くなる発声ピッチ収束が示された.したがって,発声計画中であっても入力音声が課題関連性にかかわらず発声処理に組み込まれ,音声収束が生じることが示唆された.
選考理由: 本研究では,音声収束(話者の発声が,他者の発話の音響的特徴に近づく現象)について検討している.先行研究の多くは,シャドーイング課題を用いていたため,音声収束の機序について,他者の発話への注意による説明が可能であった.それに対し,本研究では,他者の発話音声に意図的に注意を向ける必要のない課題を用いても,発声ピッチ収束(音声収束の一種)が生じることを示した.これは,音声収束が他者の発声への注意を必ずしも必要としないことを示唆し,音声知覚・生成における暗黙的なシミュレーション仮説を支持する,非常に興味深い内容である.本研究発表において,きちんと準備されたポスターを用いて,丁寧に説明がなされていた.また,多くの聴衆との議論も活発に行われており,質疑応答も含めた発表全体の質が高かった.よって,発表力評価部門での受賞に値する.
【国際性評価部門】
受賞者なし
【総合性評価部門】
受賞者(所属):武藤 拓之1,*鍵 直矢2(1.大阪公立大学大学院現代システム科学研究科 2.大阪府立大学現代システム科学域)
発表題目: 協力パートナー選択における個人手がかりと行動手がかりの統合過程―囚人のジレンマゲームを用いた検討―
発表要旨: 人は,見知らぬ他者が協力的かどうか(協力性)を判断する際,個人手がかりであるジェンダーや国籍,行動手がかりである運動の軌道などを手がかりとして利用することが知られている.しかし,ほとんどの研究は単独の手がかりの効果検証に留まっており,異なる種類の手がかりが利用可能な現実的な場面における手がかりの統合過程は明らかでない.そこで本研究は,囚人のジレンマゲームを行う2人のプレイヤーの様子を実験参加者に観察させてどちらのプレイヤーと協力したいかを選択させる実験を行い,プレイヤーの個人手がかりと行動手がかりを系統的に操作した.実験の結果,手がかり単独の効果が再現されるとともに,運動の軌道はジェンダーに優越する(実験1, N = 168) が,国籍の手がかりとは加算的に作用する(実験2, N = 168)ことが示された.これらの結果は,人が協力性判断の際に手がかりごとの信頼性を考慮し統合していることを示唆している.
選考理由: 協力パートナー選択時の協力性手がかりについて,現実場面では,複数の手がかりを同時に利用していると考えられる.本研究は,ジェンダーや国籍といった個人手がかりと,相手の選択時の行動の軌道という行動手がかりとを同時に提示した場合に,それらがどのように利用されるかを2つの実験によって検証した研究である.適切に統制された実験を実施し,ジェンダーよりは行動手がかりが優位に利用され,国籍と行動手がかりは加算的に統合されるという結果を得ており,それらの複雑な結果を網羅できる説明が提示された.手がかりの種類によって判断に及ぼす影響が異なることは,従来の単独手がかりを用いた実験では検証できないものであり,他手がかりとの関係性が変化することを見出した点にも新規性がある.また,研究内容は視覚的にわかりやすく提示され,質疑応答も明快であった.以上の理由から,本研究は,総合性評価部門の優秀発表賞にふさわしいと判断した.